自作パソコンの組み立てで必要不可欠なパーツの特集
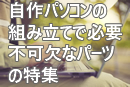
スマホ中毒でも理解できる、自作パソコンの組み立てで必要不可欠なパーツの特集を紹介しているページです。
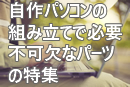
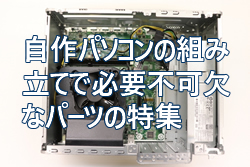
自作パソコンを作るうえで欠かせないPCパーツのことを初心者のために紹介しています。

元々グラボに強いメーカーだったので、RyzenシリーズにAMDのグラボを組み合わせた構成は、自作パソコンのみならずBTOパソコンや市販品でもトレンドになっているのです。コストパフォーマンスに優れながら、価格が控えめなことがユーザーに受け入れられております。Intelも巻き返しの攻勢を強めており、コア数やスレッド数の増加と共に、高性能なパーツを次々にリリースしているのです。
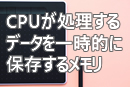
また、メモリには、デスクトップPC用のDIMMとノートPC用のSO-DIMMという2種類のサイズがあります。自作パソコンを作る場合は、基本的にDIMMを選択することになりますが、マザーボードにはSO-DIMMにしか対応していないものもあるので注意が必要です。加えて、メモリには、DDR、DDR2、DDR3、DDR4という規格があります。2021年時点で主流となっているのはDDR4ですが、これらの規格には互換性がありません。例えば、DDR3に対応したマザーボードにDDR4のメモリを使用することはできないので注意しましょう。
なお、メモリは様々なメーカーから販売されていますが、中には製造メーカーが不明なノーブランド品も存在します。ノーブランド品は、ブランド品よりも価格が安いものの品質に問題があるケースがあるので、基本的にはブランド品を選択することをおすすめします。
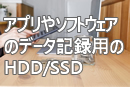
SCSIなどは、かつてのパソコンではお馴染みの端子であり、光学ドライブなどを導入するために必須の規格でした。現在は光学ドライブを内蔵せずにUSB端子で各種の機能を取り組むインターフェイスが主流のため、古い機能を使わなければ導入する必要性がありません。目的に応じて構成を変更してゆきましょう。自作パソコンならばSSDの追加も容易であり、容量を増やしたい場合には最大限まで増設することが可能です。BTOに比べて安価に増設が出来ます。
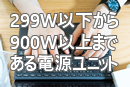
インターネット上には、パソコンを構成する各パーツを入力すると消費電力の合計値を計算してくれるサイトがあるので、その結果を電源ユニット選びの基準にしましょう。なお、電源ユニットの容量は、必要となる消費電力の2倍ほどが目安とされていますが、一般的なパーツ構成でパソコンを自作する場合は、400Wから499Wもしくは500Wから599Wのモデルで十分なはずです。
ただし、パーツ構成によっては300Wから399Wでも問題ないケースもありますし、600Wから699Wのモデルを選ぶ必要があることもあるでしょう。また、PCパーツの中でも消費電力が大きいのがグラフィックボードです。そのため、搭載するグラフィックボードの性能によっては、700Wから799Wのモデルや800Wから899Wのモデルを選ぶ必要がありますし、場合によっては900W以上でなければいけない可能性もあります。
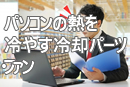
まず始めに、水冷システムとして大活躍してくれるファンですが、一番人気が高くて多く使用されているのがCPUファンになるでしょう。厚みの薄い製品が多いことや、サイズ展開も豊富にあるので自分にぴったりの商品が見つかりやすい点も魅力の一つになります。また、自作パソコンを強化したい際にケースファンを使用したり、性能をアップさせたいのであればグラフィックカードファンを使うことも良いでしょう。
最近、パソコンが直ぐに熱を持ってしまうと感じていたり、故障するのではないかと心配するような状態であれば、特殊なヒートシンクや冷却システムを導入するのも一つの手です。特にヒートシンクは放熱・吸熱を可能にした機械になるので、きっと放熱効果が高まってパソコン全体を快適にしてくれると思います。さらに、PCグリルやシリコングリスのような潤滑油を活用したり、設置が簡単なサーマルパッドを使うこともおすすめです。
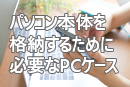
小型で且つキューブ状の形体をしているのがマイクロタワーというものです。2010年頃に販売され、自作パソコンを構築する方の間で高い人気となっています。外付けアダプタを使用すれば液晶画面の裏側に取り付けることもでき、非常に小型で置く場所を選びません。以上のPCケースを用意すれば、自作パソコンを組み立てることが可能です。
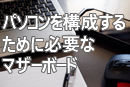
Micro-ATXは、ATXよりも一回り小さい規格になり、省スペースデスクトップやミニタワーなどに使用されいるものになります。自作パソコンでは、ローエンド設計からミドルレンジ用に向いています。Flex-ATXは、キューブ型・ブックシェルフ型のパソコンに適しているものになります。
Extended-ATXは、基盤のサイズが大きめになり、305mm×330mmの大きさです。メモリの容量が大きいといった特徴があります。XL-ATXは、ATXを横長にしたような規格になります。Mini-ITXは、主流とされている規格の中で小さい規格です。Pico-ITXは、Mini-ITXよりも小さな規格になりマザーボードのサイズは、100mm×72mmになります。一般的に自作パソコンを作成する場合は、ATXやMicro-ATX・Mini-ITXが適しています。
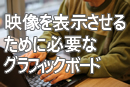
またグラフィックボードの頭脳とされるグラフィックプロセッサーを交換してみるのも良いでしょう。GPUには大きく二社があります。その一つがNVIDIA社の開発しているGPUは、NVIDIAGeForceで描画スピードが速く、万人向けと言えます。アフターサービスも手厚いと評価が高い製品です。もう一社がAMD社のRADEONというブランドのGPUです。描写能力にたけていると定評があります。自作パソコンを作る人は、こうしたグラフィックボードやGPUにこだわり、いくつか比較して作成していくとよいです。
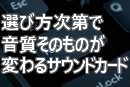
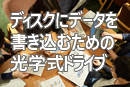
スーパーコンボドライブはコンボドライブに対応するディスクとDVD+RとDVD+RWの書き込み機能が追加されたもので、メリットはDVDへの書き込みが出来ることです。ただDVD-RやDVD-RWには書き込みが出来ないのが難点です。マルチドライブはDVDの書き込みが可能で、対応できるディスクが多いですが、他の2種と比べて価格は高いです。内蔵型だと割と安価で買えます。
選ぶときの基本は用途にあわせてブルーレイ再生がしたいならそれに対応した型、CD/DVDなどの書き込みならマルチドライブなどといって、再生だけならコンボドライブでもいいです。ブルーレイだと価格にも差があり、使わないディスクに対応しているタイプを選んでも高額になるだけで意味がありません。CPUの性能も足りてないと上手く焼けないこともあるので注意です。